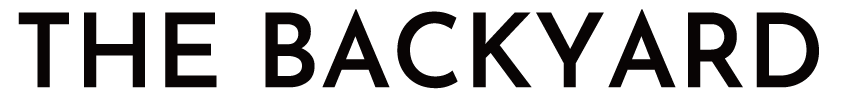
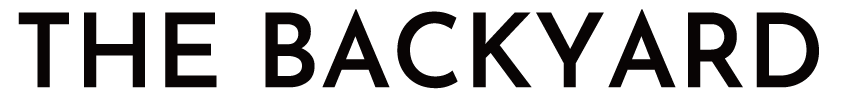
「痛みの唯一の共通点とは、他人と共有できない体験である。しかし、その共有できない痛みか ら生まれた孤独感はみんな同じだ。」と韓国の人権活動家のオムギホ氏は言う。
私が自傷行為を始めて14年も経った。両親や精神科の先生含めた周りの人たちからは、それを知られる度に「死ぬ気か?」と聞かれていた。こうした問いに当時の自分ははっきり反論することはできなかったが、その言葉に対して常に違和感覚えていた。その時の私は死への恐怖を覚えるために自傷を始め、裂いた肌色から赤色が流れてきた時、本能的に怯えた。その反応の底には、きっと生への欲求があるだろう。
言語化できない感情を目で見える形で発散したかったり、生きている証拠を感じたかったり。自分の身体に傷をつける理由やきっかけは人それぞれだと思う。だが理由は何であれ、死より生きづらさを感じながら生きることを選んだこそ、この結果に至ったのではないかと私は考えている。
自傷という言葉からは、どうしても血や刃物、病み、痛みなどを連想してしまうのだろう。私の知っている限り、自傷に焦点を当てた写真作品には、こうしたある種の痛々しい心象や現象を描写するものが少なくない一方で、は「それでも生きていく」ということに着目するものはほとんど見たことはなかった。自傷が痛々しく見えるのは事実の一部だが、その点を強調すると同時に、「この人たちは普通の人ではない」という一線も鑑賞者との間に画してしまうのではないかと思う。辛い思いを抱えたり、社会の中に生きづらさを感じたりすることは決して自傷する人だけの話ではなく、多くの人に経験されているものである。もし「普通/普通ではない」という境界線を少しでもぼかすことができたら、人々のより生きやすい世の中になるかもしれないと考えたことから、このプロジェクトを始めるに思い至った。
このプロジェクトでは、まず2021年にメンタルヘルスの助け合いサイトで自傷経験者の被写体募集の記事を掲載し、その応募者の撮影を行うことから始めた。応募者とはメールでやりとりしたのち、初顔合わせのタイミングで1時間ほど話し合いをしてから撮影に入っている。2022年に途中報告としてTOTEM POLE PHOTO GALLERYで個展を行い、その後も展示をきっかけに出会った人々の撮影や写真集の編集などを進めてプロジェクトを継続している。発表の場を通してより多くの人と出会ったからこそ、このプロジェクトは発展の機会を得て、ほんの少しでも実際に社会と関わることができた。このプロジェクトでは今後更に多くの人々の目に留まることを目指しており、人と人の繋がりを広げることで社会に影響を与えていきたいと考えている。
作家名林詩硯作品名針の落ちる音年度2023年 PITCH GRANT